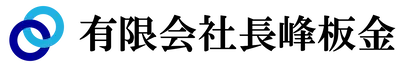屋根の構成部材
新築時には、十数年先のリフォームを考えることはあまりありません。ですから、屋根がどのように作られているのか、どのように構成されているのかもほとんど気にすることがないと思います。ですが、屋根のリフォーム(改修)時には屋根のどの構成部材までを改修範囲にするかで費用が大きく変わってくるのです。
ここでは屋根を構成している部材とその役目を紹介します。
瓦
屋根が直接的に外部環境と接する部分で、瓦の素材には粘土系、セメント(スレート)系、金属系などがあります。地震による被害から、近年ではより軽い瓦が好まれる傾向にあり、スレート系や金属系が主流になっています。一方、瓦そのものの耐用年数では、粘土系>金属系>スレート系が一般的な評価です。
棟と谷
傾斜方向の異なる屋根が接する部分には、棟・隅棟(凸部分)あるいは谷部分(凹部分)ができます。粘土系の瓦では棟・隅棟部分に棟瓦やのし瓦を載せ、スレート系や金属系では板金で棟・隅棟部分を覆い、屋根の接合部分からの雨水の侵入を防いでいます。
谷部分はいずれの瓦の場合でも板金を敷いて、谷部分に集まる雨水が瓦の下側から侵入するのを防ぎます。材質にはトタン、ガルバリウム鋼板、銅板などが使用されています。谷は枯葉やごみが溜まりやすい部分で、サビなどの劣化も進みやすく、雨漏り原因で最も多い場所です。
ルーフィング

瓦の下に敷く防水シートのことで、瓦の隙間から侵入した雨水を防水シートで防ぎ、再び瓦の隙間から排出させるようにしています。屋根防水の最後の砦と言えるでしょう。
ルーフィングの種類には、フェルト状(紙・不織布など)のシートにアスファルト、あるいはゴム・樹脂などを配合して染み込ませたもの(非透湿性)と、不織布に樹脂加工を施した透湿防水性のものとがあります。透湿防水性とは、水滴は通さないが湿気は通す性質を持ったもので、高い性能と耐久性を持っています。ですが、高価なため一般的な普及には至っていません。現在の主流は、非透湿性のアスファルト系のルーフィングで90%以上の占有率となっています。
ルーフィングは、その下地(野地板)にタッカー(大きなホッチキス)で取り付けます。また、瓦も釘やビスによってルーフィングの下にある野地板に固定します。つまり、タッカーの針や瓦を取り付ける釘・ビスはルーフィングを貫通するのですが、ゴム状のルーフィングがそれらに密着して雨水の侵入を防いでくれるのです。
しかし、当初は柔軟で柔らかいルーフィングも、経年で雨水や真夏の熱によって劣化し、硬化してしまいます。時にはひび割れることもあるのです。このような状態になってしまうと、針や釘・ビスの貫通穴にも隙間ができ、防水の役目を果たさなくなります。材質成分にもよりますが、アスファルト系ルーフィングの耐用年数は、15-20年が一般的な評価ですから、瓦の葺き替えなどに合わせて取り替えるようにしてください。
野地板
ルーフィングを敷くための下地で、構造用合板などが主に使用されています。古い住宅では、小幅板などと呼ばれる板状のものが使われている場合もあります。
垂木
野地板を取り付けるためのもので、これより下の部材は母屋や棟木などの構造材となります。